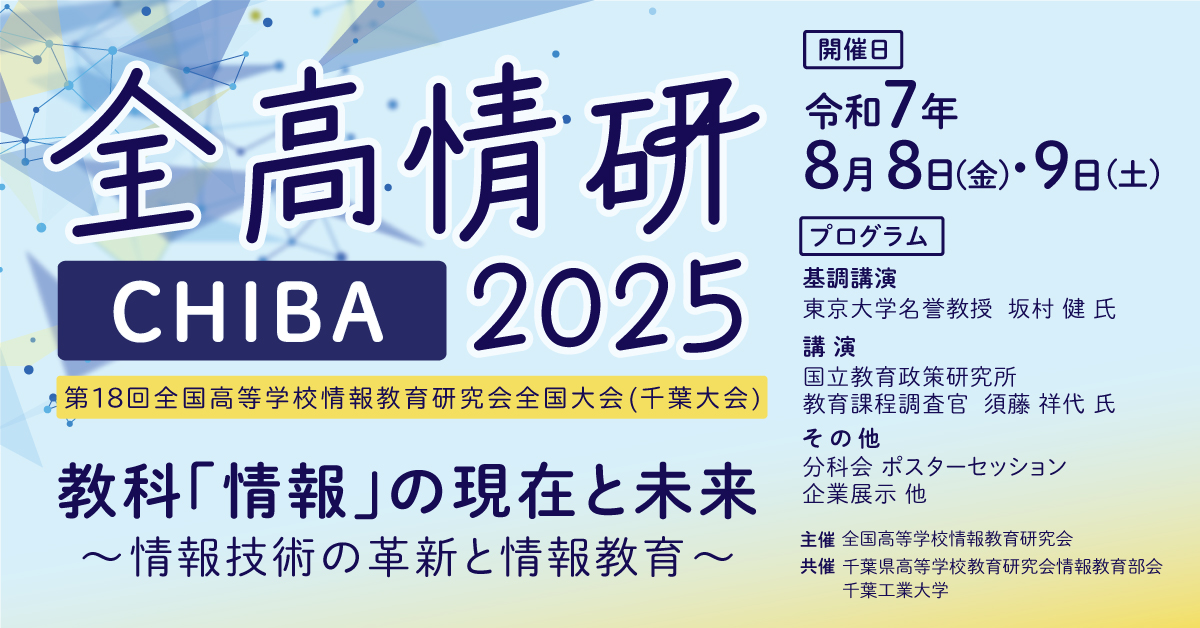日時
2025年8月8日(金曜) 15:50~16:50
2025年8月9日(土曜) 13:30~14:30
1日目(8月8日金曜)ポスターセッション 発表内容
P1-1 データ駆動型探究へと導くデータサイエンスWebアプリケーションの開発
大分県立日田高等学校 伊藤大貴
本研究の目的は,環境的な制約に影響を受けない Web アプリケーション「easyStat」「easyAutoML」の改善及び授業実践の効果を測定することである.様々な機能を新たに実装するだけでなく,多変量データを用いた機械学習を簡易に行えるよう工夫を行った.開発した Web アプリケーションを活用した授業を実践した結果,学んだ知識・技能を探究活動へ活かす様子や有意な変容を確認することができた。
P1-2 情報Ⅰの学びを「自分ごと」に変える授業とは ~情報デザインやデジタル技術との繋がりを探究できる授業の実践を通じて~
富山県立桜井高等学校 福田匡孝
情報I以降、学習内容によって生徒のモチベーションに差があると感じている。そこで、情報デザイン・デジタル技術と生徒自身との繋がりを探究できる実践を行なった。PR ウェブサイト制作や画像処理プログラム制作等を通じて仕組みや表現の面白さに気づかせ、その技術で解決したいことをテーマとした探究活動で考えを深めさせた。本実践の紹介や考察を通じ、学習内容を「自分ごと」にするための要素を議論していきたい。
P1-3 全高情研で学んだ事例を夜間定時制の授業でやってみた
群馬県立富岡高等学校 岡田聡史
昨年の全高情研愛知大会の分科会で、大阪・アサンプション国際高の岡本弘之先生が報告した「紙飛行機制作から始める問題解決・情報デザイン・データ活用の授業」を、今年度の本校の授業開きで実際に行った報告である。生徒の反応や今後の授業の展開の見通しなどについて報告したい。
P1-4 学習用小型ロボット ZRobot for micro:bit
元神奈川県高等学校情報部会 会長 元電気通信大学 客員教授 柏木隆良
高校の情報セミナーで使う学習用小型ロボットを発表します。 小型で安価に確実な動作を目標に設計・製作しました。 micro:bit でセンサとモータードライブを制御して動作。V1 はタッチ・スイッチと+超音波距離センサが備わっていますが、V2 では別のマイコンも搭載して最先端の AI センサ制御します。 www.hikonehg-h.shiga-ec.ed.jp/news/20569.html
P1-5 情報科教員と校長がタッグを組んで推進する授業改善
神奈川県立上鶴間高等学校 校長 柴田功
神奈川県立上鶴間高等学校 教諭 相馬臣彦
近年、GIGA スクール構想による生徒一人一台端末の導入や生成 AI の活用等、学校の ICT 環境は大きく変化した。こうした中、学校全体の授業改善は情報科を核にして推進することが望ましく、校長のカリキュラムマネジメントと情報科教員のリーダーシップが極めて重要である。本発表では、情報科の教員と校長がタッグを組んで、組織的な授業改善をどのように推進してきたか、その実践例を紹介するとともに、具体的な提案を行う。
P1-6 教訓を伝える童話づくりを行う情報デザインの授業実践
愛知県立南陽高等学校 三輪理人
情報デザイン分野では、スライドやポスターの作成といった形のデザインが行われることが多い。そこで本研究では、グラフィカルな部分のデザインではなく、情報そのものを工夫するデザインを行う情報デザインの実践として、教訓を伝える童話づくりを行った。本ポスターセッションでは、情報そのものを工夫することの難しさを踏まえ、生徒たちの童話づくりの実際と、実践の成果を発表する。
P1-7 GMC-4 シミュレータを活用したプログラミング単元の導入
普連土学園中学校・高等学校 渥見友章
大学入学共通テストでは、他者が作成したプログラムを読み解く力が求められる。そこで、プログラミング単元の導入として、4 ビットマイコン(GMC-4 シミュレータ)を用いたアセンブリ言語によるプログラミングを題材に扱った。与えられたプログラムをどのように修正すると、どのような変化が生じるのかに着目しながら指導を行った。本発表では、生徒の反応や、生徒が実際に作成したプログラムも併せて紹介する。
P1-8 「情報Ⅰ」とのつながりを意識した中学校技術科の教材づくり
世田谷学園中学校高等学校 山本侑
高校情報科と中学校技術科は、内容的なつながりを持たせることができる。情報Iで学ぶ要素を中学校技術科の授業においても組み込んだ教材づくりを行っている。情報通信ネットワークの授業では、腕木信号、スピーカー電話実験、増幅器製作などものづくりを通して、情報Iで学ぶデジタル化やプロトコルなどを実感し、科学的な理解を目指した。また、栽培における情報デザイン、鋳造におけるデジタル化なども紹介する。
P1-9 2025年度大学入学共通テスト「情報」の各都道府県の受験状況
電気通信大学 赤澤紀子 赤池英夫 角田博保 中山泰一
2025 年 1 月実施の大学入学共通テストで出題教科が再編され,「情報」が出題されることになった.著者らはこれまで,大学進学率に着目した情報科の第 1 学年の開講率や,教科書需要数に基づく高等学校情報科の教育現状調査を行い,都道府県ごとの特徴を示してきた.本試験当日にプレス発表する資料を基に調査分析し,「情報」の受験者数は都道府県により偏りがあること,「数学2」の受験状況が類似していることなどを報告する.
P1-10 尋ね先は「人」か「生成AI」か ~プログラミング単元における「わからないこと」への対応策~
フェリス女学院中学校・高等学校 堺和貴子
授業内で、生徒が自発的に生成 AI を利用する姿が見られるようになった。今年度「情報 I」のプログラミング単元において、実習中にわからないことがあったときに、どのような手段を多く選択していたのかアンケートを行った。本発表では、生徒が学習内容に応じてどのような対応策を選んでいたのかを事例報告し、プログラミングにおける生成 AI の利用について考察する。
P1-11 直観的な操作による画面設計が可能なWebプログラミング学習環境
四天王寺大学 本多佑希
追手門学院大学 岸本有生
大阪電気通信大学 兼宗進
プログラミング教育において、限られた授業時間の効果的活用は重要である。アプリケーション開発では、画面レイアウトの記述が煩雑で多くの時間を要するため、本質的なプログラミング思考の時間が削られる。 本研究では、教育用プログラミング言語ドリトルにおいて、直感的な操作で視覚的に画面を設計する機能を提案する。これにより、レイアウト作業時間を短縮し、ロジックの構築などにより多くの時間を割くことが可能になった。
P1-12 大学入試新課程「情報入試」導入の一事例の紹介と今後の展望
南山大学 名倉正剛 沢田篤史
「情報I」などに対応した「情報」に関する科目が,令和 7 年度入学者選抜において一部の大学で導入された.発表者の所属する大学でも一部の入学者選抜において「情報」に関する内容を追加した入学者選抜を実施した.本発表ではこの導入に至る過程と令和 7 年度入学者選抜の実施状況を,大学における「情報入試」導入の一事例として紹介し,実施状況の分析を通して今後の展望を考察する.
P1-13 「データの活用」の単元における、生成AIの活用実践について
愛知県立幸田高等学校 都築修平
データの活用の単元において、生成 AI を活用することで、主体的で対話的な学習を促進する指導方法を模索したものである。「令和5年度県立高等学校教育課程課題研究(情報)「情報通信ネットワークとデータの活用における思考・判断・表現の指導方法と評価についての研究-お菓子(グミ)の個数の偏りを題材としたグラフ化と検定-」」を参考に、身近なお菓子の内容量の違いについて、生成 AI を活用しながら仮説検定を実施した。
P1-14 大学における共通教科情報科のリメディアル授業の開発
早稲田大学人間科学学術院 望月俊男
神奈川県立横浜国際高等学校 鎌田高徳
島根大学 大﨑理乃
早稲田大学大学院 宮沢真盛
早稲田大学大学院 正司豪
早稲田大学大学院 廣瀬心咲
共通教科「情報」は大学入学共通テストに導入されたが、授業実施状況は学校間で大きく異なる。大学における情報基礎教育の一環として、ある高等学校で実施された授業内容をもとに、共通教科「情報」のリメディアル授業を開発した。データ・サイエンスは他の授業で扱うこととしたが、それ以外の内容を可能な限り含め、学部教育との整合性にも配慮した。本発表では、全 14 回の授業設計とその実践内容を報告する。
P1-15 情報科教員と生徒における生成AIの活用意向の差異と合意点を探る
山梨大学 稲垣俊介
SNS と全高情研等の ML で募ったアンケートをもとに、情報科教員と生徒が抱く生成 AI への期待・懸念・活用意向を比較した。例として、教員は「授業や自宅学習で生成 AI を使わせたい」のか、生徒は「使わせてほしい、使いたい」のかを尋ね、両者の差異と共通点を探った。さらに、利用経験と期待が活用意向を押し上げる傾向も確認した。本調査へのご協力に感謝するとともに、得られた知見を授業設計に役立つ指針として提示する。
P1-16 PyPENを自サイトに設置する
名古屋高等学校 中西渉
PyPEN は,大学入学共通テスト「情報」のプログラミング問題に似た言語のプログラミング学習環境である。公開されているものをそのまま使うこともできるが,自分が管理するサイトに設置すればサンプルや自動採点問題を差し替えることもできるので,その具体的な手順について解説する。
2日目(8月9日土曜)ポスターセッション 発表内容
P2-1 教育データの利活用によるGRIT育成の展開 ~情報科における問題解決学習(モデル化とシミュレーションのブラッシュアップを目指して)~
京都府立洛西高等学校 松本慶子
令和 8 年度の教科書改訂を見据え、情報科における「問題解決学習」を通じた GRIT(やり抜く力)育成を試みている。ベネッセスタディサポート等の質問紙データを教育ログとして活用し、生徒の非認知能力の現状を可視化してみた。今回は、モデル化・シミュレーションに焦点を当てた実践提案の紹介と、併せて本発表に参加していただいた、全国の先生方を対象としたアンケート調査も依頼したいです。
P2-2 共通テスト「情報」にどう備えたか?前任校での授業デザインを再考する
三重県立津東高等学校 池畑陽介
前任校の岡山県立高梁高等学校は、岡山県中西部の中山間地域に位置する。少子化の影響で、高梁市内の一部小中学校では全校生徒数が数十人以下となり、技術科専任教員未配置の学校がある。そのような理由から、高校入学時に情報リテラシーが十分でない生徒もいる。こうした地域的背景を踏まえながら、2025年3月に卒業した現行の学習指導要領を学習した1期生に行った大学入学共通テスト「情報」に向けた授業実践を振り返る。
P2-3 情報ニュースコーナー ~情報の”今”で拓く生徒の視野と関心~
愛知県立一宮高等学校 鈴木淳子
毎回の授業冒頭に実施している「情報ニュースコーナー」の取り組みについて紹介する。最新の情報技術から,AI,情報化社会の影の面まで,話題は多岐にわたる。 この取り組みは,ディスカッションや実体験を通じて,情報技術・情報社会がいかに現代の人々に強い影響を与えているかを考えさせる機会ともなっている。 本発表では、実際に取り上げた話題や生徒の反応などを紹介し、小さな実践の積み重ねが持つ可能性を共有する。
P2-4 触ってわかる、ネットワークの仕組み。――ProtoSim(バージョン 2)を活用した授業実践
大阪大学/金光大阪高等学校 北村 祐稀
大阪大学 長瀧寛之
追手門学院大学 岸本 有生
大阪電気通信大学 兼宗進
愛知県立旭丘高等学校 井手 広康
大阪大学 白井詩沙香
著者らは、情報Iでの活用を想定した通信プロトコルシミュレータ ProtoSim(プロトシム)を開発している。昨年の全高情研以降、先生方から寄せられたフィードバックを踏まえ、体験的な機能の増強や学びやすいデザインへの改善などを行ったバージョン 2 をリリースした。本発表では改善点を中心にデモなどを通じて授業における効果的な活用方法を示す。また、2024 年度に高校で実施した授業実践の結果を報告する。
P2-5 実生活・実社会における課題と関連付けたデータサイエンスの演習
神奈川県立横浜国際高等学校 鎌田高徳
情報IIの情報とデータサイエンスでは、データサイエンスの手法を身に付けるだけではなく、多様かつ大量のデータを活用することの有用性に気づかせることが求められる。 そこで生徒たちに企業のデータコンサルタントとなり、実生活・実社会のデータを収集させ、PPDCA サイクルに沿ってプロジェクト提案書を作成する演習を行うことで見えてきた成果と課題について報告する。
P2-6 情報Ⅰにおける授業「デジタル化」の圧縮プラン~人型ピクトグラム教材を用いて~
名古屋文理大学 御家雄一
デジタル化やデータ量計算の学習では取り扱う用語が多く,説明や読解の段階で生徒を挫折させてしまう授業を展開することを懸念する。データ量計算と量子化の部分に着目し,統一教材を横断的に使用することで,生徒の理解を促進し,授業時間の圧縮を実現した。また,パターン数を数え上げ,bit,byte を考えるフェーズで苦手意識を感じる生徒を楽しませ,計算式を考える部分で試行錯誤させた実践を報告する。
P2-7 著作権教育に必要なスキルマップの開発
広島大学 隅谷孝洋
帝京大学 天野由貴
AXIES で教育著作権の啓発と研修を重ねた経験を基に、授業で他者著作物を適切に扱うための階層的スキルマップを試作した。著作権法全体の網羅ではなく、状況別に必須知識を整理するためのものである。文化祭ステージでの音楽使用など生徒主体の場面も含め、教師が指導にも活用できる内容とした。
P2-8 「情報デザイン」お悩み相談所
私立近江兄弟社高等学校 長谷川友彦
様々な研究会等においても、「情報デザイン」に関する実践発表が少なく、もしかすると授業の案に困っている先生方も少なくないのではないかと思います。 そこで、私がこれまで積み重ねてきた「情報デザイン」に関する授業のアイデアを披露し、「情報デザイン」の授業のヒントを持って帰っていただければと思います。
P2-9 自作教材を活用したアンプラグドプログラミング授業
岡山県立倉敷南高等学校 畑英利
ソートプログラムの内容で、授業をどのように行えば生徒がプログラムの流れを理解しやすくなるのか考えた際に、カードを使って手を動かしながらプログラムをトレースする活動を取り入れれば、生徒がプログラムの流れを理解しやすくなるのではないかと思い、カード教材を自作してグループワークで授業を行った。 カードを動かしながら何回もやり直したり教え合ったりすることで、生徒は理解を深めることができていた。
P2-10 教員のキーボード操作を開示するアプリケーションの開発
千葉工業大学工学研究科情報通信システム工学専攻 山崎蓮
プログラミング教育において、教員の操作が学習者にとって視認しにくいことが,理解や模倣を困難にする要因となっている。特にコマンド入力やショートカット操作の過程が共有されない場合、初学者にとって学習の障壁となりやすい。本研究では,教員のキーボードおよびマウス操作をリアルタイムに提示する支援ツールを開発した。現在は実際の講義への導入を見据え、学習者の理解度への影響を踏まえた改善と検討を進めている。
P2-11 共通テスト対応教材作ってみた
千葉県立船橋高等学校定時制 太田剛
2025 年より共通テストで情報 I が実施されたが、まだまだ学習するための教材の整備が不十分である。そこで、過去の情報関係の試験問題を分析して、プログラミングとシミュレーションに重点をおいた教材に加えて、定番の計算問題、データサイエンス問題、確実に点をとる必要な用語・概念問題などに対応した教材を開発し Web や YouTube で公開している。
P2-12 論理素子のもったいない使い方
福井県立美方高等学校 木村文彦
これまで電子回路の工作経験は無かったが、生徒は実物を体験した方が面白いだろうと考え、論理素子を用いた授業を実践した。用いた素子は XNOR を除く6種類(NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR)、どれも1つの製品に4つずつ(NOT は6つ)回路が組み込まれていたが、そのうち1つだけを使って、素子の振る舞いを観察させた。今後は複数の素子を組み合わせた実践に繋げていきたい。
P2-13 インタラクティブウェブ教材における簡易対戦型機能の導入
千葉工業大学 工学部 情報通信システム工学科 三浦元喜
我々が公開しているウェブ教材共有サイトでは、情報科目に関連した教材を多数公開しており、誰でもブラウザやスマートフォン等から利用できる。これまでの教材は学習者間のつながりが不足していたため、我々は WebSocket を用いた汎用性の高いクライアント間情報同期の仕組みをサイトに導入した。既存のコードに少量の記述を追加するだけで簡易対戦型機能を導入し、教材の魅力を向上させることができるようになった。
P2-14 練習文生成にAIを活用したタイピング練習ソフトの開発
大阪電気通信大学 長島和平
タイピング練習では,学習者ごとに苦手なキーや入力パターンを克服することがスキル向上に繋がるとされている.しかし,個人に合わせた練習用文章を作成する手間が大きく,苦手なキーに対応した文章形式のタイピング練習システムは少ない.本研究では,学習者ごとに最適化されたタイピング練習を実現することを目的に,練習記録をもとに AI を活用して苦手な入力パターンを含む練習用文章を自動生成する仕組みを提案する.
P2-15 「情報」を大学入試に導入して見えたこと ~電通大 2025年度情報入試の実践報告〜
電気通信大学 小宮常康
電気通信大学 渡辺博芳
電気通信大学 中山泰一
電気通信大学 成見哲
電気通信大学では,2025 年度入試より,一般選抜前期日程においてこれまで必須であった個別試験科目「数学」「英語」「物理」「化学」に新たに「情報」を加え,「物理」「化学」「情報」については,これら 3 科目から 2 科目を選択する科目選択制へと変更した.本発表では,その最初の個別試験「情報」の実施概要について,受験状況や合格者の声などを提示できる範囲で紹介し,そこから見えたことについて報告する.
P2-16 生成AIでつくる「30歳のわたし」
私立関西創価高等学校 辻誠一
かつて稲垣先生が発表した「30 歳のわたし」の発展形。自分の職業や興味のある事を、生成 AI の Geminiを使用して、2040 年がどのように変わっているかを参考文献を基に Gemini に予想させる。そして、自分の将来の職業についているかをポスターにして Web サイトに公開。生徒同士で相互評価する授業をした。 2040 年の予想は Gemini の回答しか書いてはいけないという縛りの中で生徒が悪戦苦闘ぶりを紹介。
P2-17 大学入試を中心とした情報分野の学力評価手法の検討〜第3報~
京都産業大学 安田豊
慶應義塾大学 植原啓介
電気通信大学 角田博保
東京通信大学 筧捷彦
國學院大學 高橋尚子
放送大学 辰己丈夫
日本大学 谷聖一
工学院大学 中野由章
電気通信大学 中山泰一
大阪学院大学 西田知博
大阪大学 萩原兼一
獨協医科大学 坂東宏和
令和 7 年度入学者選抜から、共通テストをはじめ「情報」科目の出題が増えている。「情報」は他の教科に比べて歴史が浅く、十分に学力評価手法が確立していないため、情報分野の知識体系の整理と学力評価手法の確立を目指して研究を行っている。典型的な問題および多肢選択問題で学習成果測定のための作問手順書作成は目標の一つで、模擬試験をこれまでに二回実施した。模擬試験の概要と結果の比較および今後の計画を紹介する。
★企業展示★ポスター番号順★
K-1 株式会社アルファコード K-2 カシオ計算機株式会社 K-3 学校法人京都産業大学 K-4 GMO メディア株式会社 K-5 システム・エボリューション株式会社 K-6 実教出版株式会社 K-7 株式会社スクーミー K-8 ソフトバンク株式会社 K-9 株式会社ナカヨ K-10 日本データパシフィック株式会社 K-11 日本文教出版株式会社 K-12 paiza 株式会社 K-13 一般社団法人ミラパブ K-14 特定非営利活動法人みんなのコード K-15 ライフイズテック株式会社 K-16 株式会社技術評論社 K-17 株式会社サーティファイ K-18 株式会社グッドワークス K-19 iJapan 株式会社 K-20 株式会社ナリカ K-21 株式会社インプレス K-22 数研出版株式会社 K-23 株式会社クリプトン K-24 株式会社オデッセイコミュニケーションズ K-25 株式会社インフォザイン K-26 CQ 出版株式会社 K-27 東京書籍株式会社 K-28 東京法令出版株式会社 K-29 株式会社内田洋行 K-30 ケニス株式会社 K-31 株式会社教育と探求社 K-32 株式会社大修館書店 K-33 株式会社キャリアナビゲーション K-34 東京大学 情報基盤センター K-35 一般社団法人 デジタル人材共創連盟