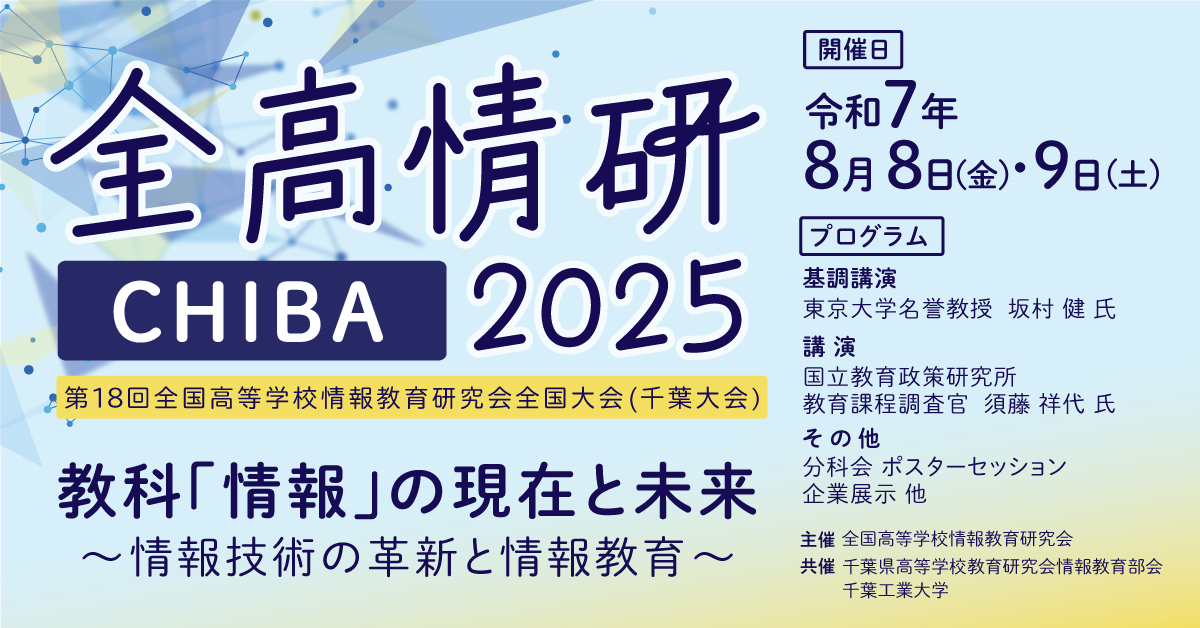タイムテーブル下にある「発表要旨」を開くと,セッションごとに発表要旨を見ることができます。
2025年8月8日(金曜)
| 分科会A 611会議室 |
分科会B 612会議室 |
分科会C 614会議室 |
分科会D 615会議室 |
|
|---|---|---|---|---|
| セッション1 14:20 ~ 14:45 |
A-1 T高校における共通テスト情報Ⅰ対応戦略「生徒アンケートから見える課題と可能性」 |
B-1 「情報デザイン」授業実践報告のテキストマイニングによる分析 Part2 | C-1 プログラミング学習の多様化を目指すための小型カー開発 | D-1 プログラミングの授業 段階を踏んでやってみた |
| 東大寺学園中学校・高等学校 𠮷田 拓也 発表スライド |
帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 天野 由貴 発表スライド |
秋田県立秋田北鷹高等学校 川村 幸生 発表スライド |
アサンプション国際高等学校 岡本 弘之 発表スライド |
|
| セッション2 14:50 ~ 15:15 |
A-2 情報Ⅰの年間指導計画からみる特徴や工夫、課題の事例紹介 | B-2 情報デザインの単元を全て主体的学習にしてみた | C-2 生成AIによるプログラミング支援システムの開発とマイコンボードへの活用 | D-2 情報Ⅰのプログラミング教育に生成AIを利用することの是非 |
| 埼玉県高等学校情報教育研究会 泉田 駿 発表スライド |
西宮市立西宮東高等学校 真田 和樹 発表スライド |
元東京都立日比谷高等学校・元東京学芸大学 天良 和男 発表スライド |
愛知県立旭丘高等学校 井手 広康 発表スライド |
|
| セッション3 15:20 ~ 15:45 |
A-3 データサイエンスプレゼンテーションの授業実践 | B-3 自己有用感を熟成する情報デザインの指導方法の模索 | C-3 「和歌を情報学的な視点で見てみよう」教科書横断的な学習の実践報告 | D-3 探究的にプログラミングを学ぶ情報Ⅰ授業 |
| 愛知県立高蔵寺高校学校 田中 健 発表スライド |
横浜市立戸塚高等学校定時制 杉山 大海 発表スライド |
千葉県立柏の葉高等学校 浅見 智峰 発表スライド |
岡山理科大学 高橋 信幸 京都府立乙訓高等学校 河端 梓 発表スライド |
A-1 T高校における共通テスト情報Ⅰ対応戦略「生徒アンケートから見える課題と可能性」
東大寺学園中学校・高等学校 𠮷田 拓也
2022年1月、「2025年国立大学入試に『情報Ⅰ』が追加される」というニュースが報じられ、情報科教育の状況は大きく変化した。本稿では、2022年4月に始まった新科目「情報Ⅰ」に対するT高校独自の取り組みや、そこで重視してきたポイントを整理する。また、「情報Ⅰ」の全授業を終えた直後に実施した生徒アンケートを基に、生徒たちの期待や不安、授業の成果を分析した。やはり、生徒たちの声こそが最も重要である。
B-1 「情報デザイン」授業実践報告のテキストマイニングによる分析 Part2
帝京大学ラーニングテクノロジー開発室 天野 由貴
「情報I」では新たに「コミュニケーションと情報デザイン」の単元が追加され,2022年度より実施されている.本稿では「情報デザイン」が高校の授業の中でどのように取り扱われているか,関連論文をテキストマイニング手法によって傾向分析する。
特に情報デザインをおこなう上で,コミュニケーションの「目的」が意識されているかを調査する。
C-1 プログラミング学習の多様化を目指すための小型カー開発
秋田県立秋田北鷹高等学校 川村 幸生
高校情報科におけるプログラミング学習の多様化を目的として,ボード型コンピュータと計測・制御モジュールを配置したツールボックス,およびボード型コンピュータ制御の小型カーを製作した。小型カーの手動制御を手順化する過程はアルゴリズム学習の基礎になるとともに,小型カーに計測・制御モジュールを取り付け自律的走行するためのプログラムを作成する過程はプログラミング学習を深める。
D-1 プログラミングの授業 段階を踏んでやってみた
アサンプション国際高等学校 岡本 弘之
情報Ⅰでプログラミングが必須となり、共通テストをにらんでも実習させておくことが必要である。その一方コードを使って生徒が創意工夫することは難しいので、授業では「アルゴロジック→Scratch→Pythonの基本→ロボットプログラミング→Pythonでシミュレーション」とステップを踏んで授業実践を行った。発表ではこの授業の目的や具体的な内容と生徒の反応について紹介する。
A-2 情報Ⅰの年間指導計画からみる特徴や工夫、課題の事例紹介
埼玉県高等学校情報教育研究会 泉田 駿
埼玉県内の高校における情報Ⅰの年間指導計画から学習指導要領における各内容の取扱時間を調査比較したものを報告する。調査の結果,多くの学校で情報Ⅰの内容を全て教えるための時間が不足していた。この問題に対して,各研究委員の所属校における指導方法の工夫など様々な事例を紹介する。本発表が全国の情報科教員にとって有益な情報共有となり,各校における情報Ⅰのより良い指導計画作成の一助になることを期待する。
B-2 情報デザインの単元を全て主体的学習にしてみた
西宮市立西宮東高等学校 真田 和樹
筆者自身は冬休み明けに情報デザインをする予定だったが、授業計画を立てたら確保できるのが1コマしかなかった。そこで、自転車交通安全に関するもの、ポケットティッシュサイズのポスターを制作する2つだけ生徒に提示し、全て生徒に各自で任せ、授業時間外で行ってもらった。学習のインプットからポスター制作まで全て主体的学習にさせた結果と考察を述べ、これからの主体的な学習のあり方について考える。
C-2 生成AIによるプログラミング支援システムの開発とマイコンボードへの活用
元東京都立日比谷高等学校・元東京学芸大学 天良 和男
生成AIを使ったプログラミング支援システムの多くはPC上での入出力に留まっている。本システムでは,プログラミング言語に不慣れな初心者であってもアルゴリズムを示す指示文を入力するだけで,生成AIが出力したコードをPCに留まらずマイコンボードに直接転送・実行でき,ロボットや鉄道模型等の制御を通してプログラミング的思考力を習得することができる。また出力調整機能により安易にAIへ依存しないよう制限できる。
D-2 情報Ⅰのプログラミング教育に生成AIを利用することの是非
愛知県立旭丘高等学校 井手 広康
情報Ⅰのプログラミング教育において生成AIの利用を許可した実践を行った。本実践の「プログラムの自由制作」の活動において,実際に生徒らが生成AIを使用した画面は,①題材の提案,②プログラムの生成,③デバッグの三つであった。本研究では,生徒の制作物や事後アンケート,授業者の所感などから,情報Ⅰのプログラミング教育に生成AIを利用することの是非について考察する。
A-3 データサイエンスプレゼンテーションの授業実践
愛知県立高蔵寺高等学校 田中 健
情報Ⅰの単元「データの活用」の授業展開例として、生徒自身が仮説を立て、その検証のために主体的に取得したデータを突き合わせることで結論を導く、データサイエンスの一端を経験させる活動が有用である。本発表では、筆者の勤務校で2024年度に実施した、その過程と結論を最終的にプレゼンテーションに落とし込ませるデータサイエンスプレゼンテーションの授業実践について報告したい。
B-3 自己有用感を醸成する情報デザインの指導方法の模索
横浜市立戸塚高等学校定時制 杉山 大海
本発表は令和6年度に戸塚高等学校定時制で3年生に対して行った「情報デザイン」の実践報告である。生徒たちに自信を持たせ、自己有用感をはぐくむことをねらいとして、学校や地域から作品のオファーにこたえる活動を取り入れた。その成果と課題についてまとめ、より充実した活動を行うための手立てについて考察する。
C-3 「和歌を情報学的な視点で見てみよう」教科横断的な学習の実践報告
千葉県立柏の葉高等学校 浅見 智峰
情報理数科の生徒を対象に、「各々が他教科のシラバスから好きな単元を選び、情報Iで取り扱う範囲と視点で再構成・再解釈してみよう」という授業を行った。本発表では国語科の「和歌」を題材とし、意味の圧縮性や文脈依存性を”データの圧縮”や”暗号化”、”メディアの種類”などをつかって解釈した例について報告する。
D-3 探究的にプログラミングを学ぶ情報Ⅰ授業
岡山理科大学 髙橋 信幸
京都府立乙訓高等学校 河端 梓
本研究では探究的なプログラミング教育のプログラミング的思考力への影響を探った.情報Ⅰ授業にて,コーディング指導と教育用ドローンを用いた探究的プログラミング教育を併せて実践し,その効果を分析した.その結果,探究的な学びによってプログラミングの楽しさや達成感を実感する生徒の割合が増して主体的に取り組む態度育成に寄与することや,順次・分岐・繰り返しや変数などの知識の獲得が促進されたことが認められた。
2025年8月9日(土曜)
| 分科会A 611会議室 |
分科会B 612会議室 |
分科会C 614会議室 |
分科会D 615会議室 |
|
|---|---|---|---|---|
| セッション4 09:30 ~ 09:55 |
A-4 高等学校「情報Ⅰ」における生徒が生成AIの役割を自ら切り替えて問題解決に取り組む授業の実践 |
B-4 情報Ⅱを想定した階層型クラスタリングの授業実践 |
C-4 生徒の体験と物語創作を通したメディアリテラシー教育 |
D-4 不登校経験や外国にルーツを持つ生徒に対応した情報科授業の実践 |
|
大成高等学校 |
追手門学院大学 岸本 有生 四天王寺大学 本多 佑希 大阪電気通信大学 兼宗進 発表スライド |
愛知県立緑丘高等学校 橋本 正隆 発表スライド |
東京都立一橋高等学校 喜多 智美 発表スライド |
|
| セッション5 10:00 ~ 10:25 |
A-5 生徒が主体的に学習に取り組む情報Ⅰにおける実践 | B-5 教科情報での学びを探究で応用させるには |
C-5 学校設定科目「情報学基礎」における生成AIに関するリテラシーを涵養する授業実践 |
D-5 挑戦と成長を促す「全範囲自由進度学習」の実践報告 |
|
東京都立三鷹中等教育学校 |
京都産業大学附属中学校・高等学校 |
京都市教育委員会 中村 央志 発表スライド |
東京都立小岩高等学校 椋本 哲也 発表スライド |
|
| セッション6 10:30 ~ 10:55 |
A-6 情報Ⅰ4回転授業モデル |
B-6 ソフトウェアテストを意識したプログラミング教育 |
C-6 プロンプトリテラシーの向上を目指した授業と評価 |
D-6 DXハイスクールにおけるウェアラブル端末を活用したデータサイエンス実習 |
| 千葉県立船橋啓明高等学校 谷川 佳隆 発表スライド |
千葉県立沼南高等学校 |
お茶の水女子大学附属高等学校 山上 通惠 発表スライド |
福岡県立糸島高等学校 長江 一範 発表スライド |
|
| 10:55 ~ 11:05 |
休憩 | |||
| セッション7 11:05 ~ 11:30 |
A-7 この素晴らしい情報Ⅰに情報法を! | B-7 理系全員必修に向けた情報Ⅱの授業計画と外部連携 |
C-7 コンピュータの起源を通してコンピュータの仕組みを学ぶ授業実践 |
D-7 論理回路の設計を体験できるブラウザ学習教材の開発と実践 |
| 中央大学杉並高等学校 生田 研一郎 |
雲雀丘学園中学校・高等学校 林 宏樹 電気通信大学 渡辺 博芳 発表スライド |
神奈川総合産業高等学校 大石 智広 発表スライド |
名古屋市立緑高等学校 小林 裕司 発表スライド |
|
| セッション8 11:35 ~ 12:00 |
A-8 ワクワク情報Ⅰ:総ざらい実習指導実践と生徒成果物事例 | B-8 生徒が主体となって進める情報Ⅱの授業実践報告 |
C-8 情報科の「中核的な概念」を段階的に学ぶ教材の開発 |
D-8 ネットワーク基礎理解を目的としたピクトコルシミュレータによる指導実践 |
|
東京都立松が谷高等学校 |
東京都立立川高等学校 阿部 百合 発表スライド |
ノートルダム清心女子大学 大西 洋 発表スライド |
樟蔭中学校・高等学校 川浪 隆之 高田 真理 発表スライド |
|
| セッション9 12:05 ~ 12:30 |
A-9 「データの活用」問題解決学習の実践と課題 | B-9 10年目(相当)の「情報Ⅱ」実践──普通科高校における年間授業モデル |
C-9 高等教育につなぐ情報教育の実践 |
D-9 プログラミング指導方法の分類と生徒の手が止まったときの教材改善 |
| 東京都立国立高等学校 小原 格 発表スライド |
日出学園中学校・高等学校 武善 紀之 発表スライド |
麗澤中学校・高等学校 野口 紘司 発表スライド |
佼成学園中学校高等学校 岡野 英樹 発表スライド |
|
A-4 高等学校「情報Ⅰ」における生徒が生成AIの役割を自ら切り替えて問題解決に取り組む授業の実践
大成高等学校 萩原 浩平
情報Ⅰでは,問題解決の一連の活動を通して資質・能力を育むことが重要とされている.また,近年生成AIの活用が注目されており,問題解決による学びを促進することが期待される一方,活用の仕方によっては生徒の学びが失われることが懸念される.そこで,本研究では情報Ⅰにおける問題解決の学びを促進させることを目的とした.具体的には,生徒が生成AIの役割を自ら切り替えて問題解決に取り組む授業を行い,効果を検証した。
B-4 情報IIを想定した階層型クラスタリングの授業実践
追手門学院大学 岸本 有生
四天王寺大学 本多 佑希
大阪電気通信大学 兼宗進
情報IIでは、階層型クラスタリングが紹介されている。しかし、実習にPythonが必要で、変数の標準化、クラスタリング手法の選択、距離閾値の設定など取り扱いは難しい。そこで、データ分析学習システムConnect DBに階層型クラスタリングを実行できる機能を追加した。飲料の成分データを題材に、生徒は散布図行列でデータ全体を把握し、階層型クラスタリングで分類をしながら、どの成分が影響するかを学習する。
C-4 生徒の体験と物語創作を通したメディアリテラシー教育
愛知県立緑丘高等学校 橋本 正隆
メディア体験の振り返り・共有、要素分析、グループでのストーリー創作を通したメディアリテラシーに関する授業を設計・実践した。メディア体験を他者と相対化することで俯瞰的視点を獲得し、対話を通してメディアとの多様な関わり方を学び取ることが示唆された。また創作活動は生徒の本音を引き出す効果も確認された。一方、効果的に展開するための内容の精選や、評価手法の確立など実践上の課題も明らかになった。
D-4 不登校経験や外国にルーツをもつ生徒に対応した情報科授業の実践
東京都立一橋高等学校 喜多 智美
本校には、不登校経験や外国にルーツをもつ生徒、ICTに不慣れな生徒や中学校技術の情報分野を十分に学べなかった生徒など、多様な背景をもつ生徒が在籍している。情報Ⅰを中心に、情報Ⅱや学校設定科目を含めた授業の中で、ルビや翻訳ツールの活用、視覚に配慮した資料、実習重視の構成、振り返りによる学びの定着支援などの工夫を行ってきた。本発表では、こうした生徒に対応する情報科授業の取り組みと課題について報告する。
A-5 生徒が主体的に学習に取り組む情報Ⅰにおける実践
東京都立三鷹中等教育学校 能城 茂雄
VUCA時代(将来の予測が困難な状況)に対応するには、知識詰め込み型の教育から、学びの在り方を大きく転換する必要がある。情報Ⅰは特に内容の進展・変化が激しく、生徒の主体的な学びが重要となる。令和6年度は、生徒の主体的な活動に軸を置いた授業を実践した。本発表では、コンピューティング・プログラミング・ネットワークの授業実践を通して、生徒の主体性を育む新たな学びの可能性を提案する。
B-5 教科情報での学びを探究で応用させるには
京都産業大学附属中学校・高等学校 森本 岳
教科情報では情報Ⅰ・Ⅱにおいて、問題の発見・解決に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力を身につける。情報で身につけた力は、その後の総合的な探究の時間にどのように活かすことができるのか。それを明確にすることで、情報を学ぶ意義もより高まるのではないか。探究での実践例をパターン化して整理することで、その手法や可能性について共に考えたい。
C-5 学校設定科目「情報学基礎」における生成AIに関するリテラシーを涵養する授業実践
京都市教育委員会 中村 央志
京都市立西京高等学校では、情報科の学校設定科目「情報学基礎」において、プログラミングの内容を終えた後の授業で、プログラミングの観点を踏まえた生成AIに関するリテラシーの涵養を目的とした授業実践を行った。授業では、ゲームAI、リアルタイム物体検出AI、対話型生成AI、画像生成AI、ディープフェイクをグループごとに体験させ、それぞれのAIに関する利点や問題点を考察し、発表を行った。本発表では、授業実践の内容および生徒のAIに関する考察や感想について報告する。
D-5 挑戦と成長を促す「全範囲自由進度学習」の実践報告
東京都立小岩高等学校 椋本 哲也
生徒それぞれが自分のペースで学ぶ「全範囲自由進度学習」を目指した情報Ⅰの実践報告。最初に学びたい範囲を自ら選択し、必須課題と追加課題の複線的な学習構造により一人ひとりの興味関心に合わせた深い学びを実現する。口頭試問や相互教授、プログラミング実践などの多様な学習活動を通じて主体性を育み、ルーブリックによる評価基準の明示、進捗を可視化するダッシュボード、毎回のPDCAサイクルで自己調整能力を育成する。
A-6 情報Ⅰ4回転授業モデル
千葉県立船橋啓明高等学校 谷川 佳隆
従来,情報Ⅰの授業は教科書の章立てに沿って展開していましたが,必ずしも章を順に教える必要はありません。各章の内容は独立ではなく相互に関連しており,それぞれを横断的に扱うことで,より効果的な学習が可能ではないかと考えました。そこで,各章を4分割し,2?4回程度授業を行った後,別の章へと進む「4回転授業モデル」を1年間実施しました。本稿では,その実践内容と生徒アンケート結果をもとに効果を報告します。
B-6 ソフトウェアテストを意識したプログラミング教育
千葉県立沼南高等学校 沼崎 拓也
情報Ⅱではシステム開発の内容で単体テストや結合テストなどが扱われる。テストを書いてからプログラムを作成し、テストを通過する状態になれば完成と判断する「テスト駆動開発」の考えに基づけば、情報Ⅰのプログラミングにもテストの概念は利用可能である。Pythonのテストライブラリを使用したテスト駆動のプログラミング教育について提案し、また生成AIが出力するコードとテストとの関係について考察し発表する。
C-6 プロンプトリテラシーの向上を目指した授業と評価
お茶の水女子大学附属高等学校 山上 通惠
生成AIは瞬く間に世界に広がり,後発のサービスでは画像・音声・動画生成などの機能も持ち,高校生も日常的に利用している。本稿では,生成AIの活用において不可欠とされるプロンプトリテラシーの向上を「問題解決力」の文脈で位置づけ,高等学校学習指導要領(情報I)において育成が求められる「情報社会の問題解決」「コミュニケーションと情報デザイン」などとの関連を意識した授業の展開や評価の手法を整理し,検討する。
D-6 DXハイスクールにおけるウェアラブル端末を活用したデータサイエンス実習
福岡県立糸島高等学校 長江 一範
DXハイスクールの一環でウェアラブル端末を用いて睡眠に関する生体データを収集し、自身の健康を考えるデータサイエンス実習を実施した。先行事例が無かったため、計画の立案や端末の調達・生体情報の取り扱い・参加同意書の作成・不参加者への対応など事前にクリアすべき課題が多々あった。高大連携による睡眠研究の専門家による講演・助言を基に実習を行い、数理課題と考察レポートによるルーブリック評価を行った。
A-7 この素晴らしい情報Ⅰに情報法を!
中央大学杉並高等学校 生田 研一郎
皆さんも情報の「社会」科学的な理解を扱ってみませんか? プログラミングやデータサイエンスと同様、情報法も情報社会の重要な一分野です。情報社会の理解にはバランスの良い授業が必要です。 「個人情報」「プライバシー」「肖像権」「パブリシティ権」の抑えどころを1コマでまとめた授業実践報告です。授業ですぐに使えるであろう話題をお持ち帰り頂けたら幸いです。
B-7 理系全員必修に向けた情報Ⅱの授業計画と外部連携
雲雀丘学園中学校・高等学校 林 宏樹
電気通信大学 渡辺 博芳
DXハイスクール事業採択校である本校は,2026年度より高校2年理系選択者全員が「情報Ⅱ」を履修する。本発表ではその授業計画を報告する。授業は基礎を学ぶ「習得フェーズ」と応用する「探究フェーズ」で構成する。探究フェーズでは生徒が主体的に課題を設定し,データ収集・分析,モデル構築,システム開発を行い,成果を外部コンテストで発表することを目指す。授業実践に向けて,動画教材制作・活用,大学連携等を進める。
C-7 コンピュータの起源を通してコンピュータの仕組みを学ぶ授業実践
神奈川総合産業高等学校 大石 智広
「どんな特徴を備えることでコンピュータはコンピュータになったのか」という単元を通した問いを軸に、情報Iの「(3)コンピュータとアルゴリズム」の内容を探究的に学習する授業実践をおこなった。パスカル、バベッジ、シャノンのうち誰がコンピュータにとって最も本質的な特徴を生み出したのかを考察することを通して、単元の内容を探究的に学習することを目指した。本発表では、授業設計や生徒の学びの様子について報告する。
D-7 論理回路の設計を体験できるブラウザ学習教材の開発と実践
名古屋市立緑高等学校 小林 裕司
本発表では、JavaScriptにより実装したCPU回路設計体験教材を紹介する。生徒はページの指示に従いクリック操作をすることで、入力信号のオン/オフや論理ゲートの種類を順番に切り替えることで、論理回路の動作を体験的に学習する。これにより真理値表など知識の学習だけでなく、加算器の仕組みなど応用的な理解の達成を目標としている。また、授業内評価として操作ログ解析を用いた客観的指標の検討・実践も試みる。
A-8 ワクワク情報Ⅰ:総ざらい実習指導実践と生徒成果物事例
東京都立松が谷高等学校 布村 覚
情報Ⅰを学ぶ生徒が、習得したリテラシーを進路と関連付け、自主的に探究を深められるよう関心を高めることが重要である。本報告では、限られた時間とリソースで行ったプログラミング以外の領域と連携した長尺実習実践を紹介する。統計分析を活用した探究学習の成果物を基に、メディア統合によるライトニングトーク動画作成、HTMLによるコンテンツ実装、バイナリエディタによるヘッダ解析等、楽しさを踏まえ多面的に展開した。
B-8 生徒が主体となって進める情報IIの授業実践報告
東京都立立川高等学校 阿部 百合
1年目の進め方とその成果と反省、2年目の今年の様子と展望を共有します。 1年目は、前半は教科書を用いて生徒が解説と実習を展開、後半は各自の興味による探究、最後は情報I入試演習でした。 教科書をなぞるのではなく、より深く展開できるようファシリテーターとしてどのように教材研究や授業準備をし、声かけやしかけをしたか、もお話します。
C-8 情報科の「中核的な概念」を段階的に学ぶ教材の開発
ノートルダム清心女子大学 大西 洋
学習指導要領の改訂に向けた諮問では、各教科で「中核的な概念」等を中心とした内容の構造化が求められた。本発表では、高校生が情報科の「中核的な概念」を段階的に学べるよう、「コミュニケーションと情報デザイン」の冒頭での使用を想定して開発した教材を紹介する。教材は記号論を基礎とし、基礎情報学・社会システム論に基づく授業実践の知見を取り入れた。その上で、開発した教材で自由参加型の講座を行った結果を報告する。
D-8 ネットワーク基礎理解を目的としたピクトコルシミュレータによる指導実践
樟蔭中学校・高等学校 川浪 隆之 高田 真理
ルーティングの学習は、実機ルーターを使うには準備や費用がかさみ、扱いが難しい場面も多い。そこで、ブラウザ上で使える「ピクトコルシミュレータ」を授業に導入した。データの流れを視覚的に追えるため、生徒は興味を持って積極的に取り組んでいた。また、小テスト機能もあり、生徒の理解度確認にも非常に役立った。限られた時間と環境でも効果的にルーティングを理解できる方法として、その実践と授業での工夫を報告する。
A-9 「データの活用」問題解決学習の実践と課題
東京都立国立高等学校 小原 格
「情報通信ネットワークとデータの活用」における問題発見・解決型のデータ活用実習についての実践報告を行う。PPDACサイクルも意識させ、問題を発見しそれをデータで表現するとともに、さらに別の2つの根拠・改善案等のデータを示し、結論を明示させる問題解決学習を行った。生徒は概ね良く取り組んだが、ゴールの示し方や進め方、共通テストへの対応など、教員による課題の与え方についてさらに工夫の余地が見られた。
B-9 10年目(相当)の「情報Ⅱ」実践──普通科高校における年間授業モデル
日出学園中学校・高等学校 武善 紀之
本校では2024年度より高3生に「情報Ⅱ」を選択開講しているが、旧課程でも「社会と情報」の発展科目として「情報の科学」を選択開講し、「情報Ⅱ」の素地を育んできた。今年度は、こうした実践の10年目にあたる。本発表では「情報Ⅱ」の授業モデルとして、年間の構成に加え、2学期前半まで実施する「分野別ミニ実習」、2学期後半以後行う「卒業制作・研究」の実施具体例をそれぞれ報告する。
C-9 高等教育につなぐ情報教育の実践
麗澤中学校・高等学校 野口 紘司
高等教育へ接続するためのアプローチとして、認知能力だけではなく非認知能力もバランスよく育むことが重要である。中高一貫校である本校では、大学入学共通テスト対策講座だけではなく、中学技術と高校情報Ⅰ・Ⅱにおいて、ティンカリングを取り入れた電子工作IoTプログラミングの授業を実践している。DXハイスクール採択校でもある本校の、デジタルファブリケーションツールを活かした取り組みについて報告する。
D-9 プログラミング指導方法の分類と生徒の手が止まったときの教材改善
佼成学園中学校・高等学校 岡野 英樹
プログラミングの指導方法は多岐にわたる。その指導方法の分類をし,それぞれのメリットやデメリットについてまとめる。また,プログラミング実習において生徒の手が止まってしまった場合に,来年度以降どのように教材を変更していけばよいかについて触れ,変更した際のビフォーアフターの結果をデータやグラフでにまとめて説明する。